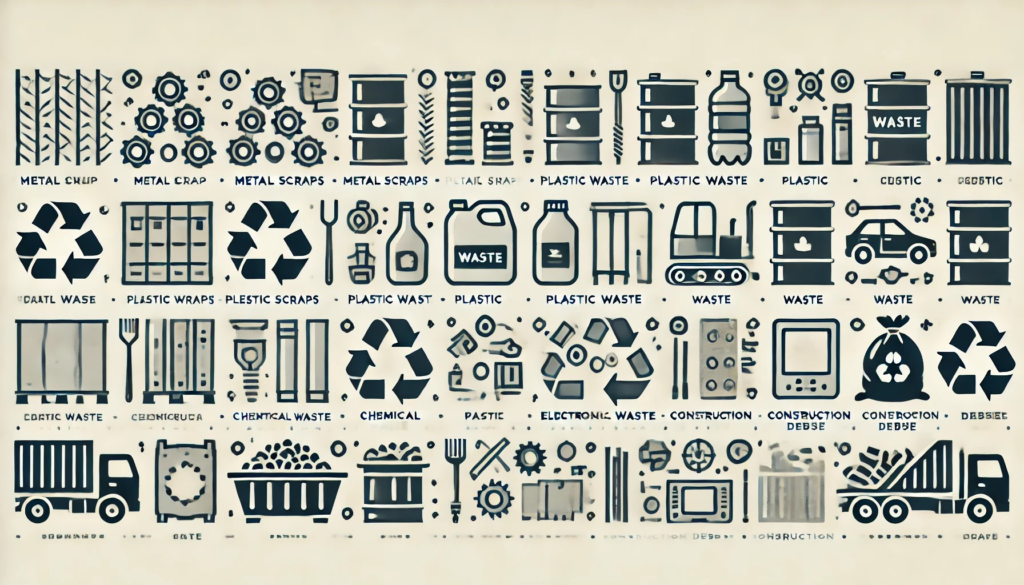目次
- はじめに:地方移住×農業の魅力
- 農業を始めるための法的な基礎知識
- 農地取得・賃借の手続き
- 地方移住で利用できる主な補助金・助成金
- 新規就農者向け補助金・支援制度の例
- 農業法人化やビジネス展開を視野に入れる場合
- 農業を始めるにあたって押さえておきたいポイント
- まとめ:行政書士を活用してスムーズな農業スタートを
1. はじめに:地方移住×農業の魅力
近年、「地方移住をして農業を始めたい」という相談が増えています。リモートワークの普及や、自然豊かな環境での暮らしへの関心が高まっていることも要因の一つです。
- 豊かな自然の中で自給自足に近い生活を送れる
- 地域コミュニティの活性化に貢献できる
- 国や自治体からのサポート体制が充実している
こうしたメリットがある一方、法的な手続きや補助金制度などを正しく理解していないと、思わぬトラブルに直面することがあります。本記事では、新しく農業に挑戦するうえで押さえておくべきポイントを行政書士の視点から解説していきます。
2. 農業を始めるための法的な基礎知識
農地法(農地を扱うための基本法)
農地を「借りる」「買う」「転用する」など、農地を扱う際にまず知っておきたいのが**「農地法」**という法律です。
この法律は、農地を守り、有効に活用することを目的に定められています。具体的には、以下のような点が重要です。
- 農地の売買や賃貸借には、農業委員会の許可が必要(農地法第3条)
- 農地を宅地や駐車場など、農地以外の用途に変える(転用)には制限がある(農地法第4条・第5条)
大切なのは、「実際に農業(耕作)の目的で利用する人」以外は、基本的に農地を取得・利用することができないということです。たとえば、農家や農業法人などが該当します。
これから農業を始めたいと思っている方(新規就農者)も、農地を借りたり購入したりする場合には農業委員会の許可が必要になります。許可を受けるためには、耕作や経営に関する計画などをしっかり準備しておくことが求められます。
農業委員会と農地取得
市町村ごとに設置されているのが**「農業委員会」**です。農地の貸し借りや売買、あるいは転用などについて、許可や審査を担当しています。
農地を借りたり買ったりする場合は、次の点を覚えておきましょう。
- 賃借(農地を借りる場合)
- 農地を借りる際は、農業委員会の許可(農地法第3条)を受ける必要があります。
- 購入(農地を買う場合)
- 原則として、農地を購入する際にも農業委員会(または都道府県知事等)の許可(農地法第3条)が必要です。
- 許可されるかどうかは、購入希望者の農業経験や地域の状況などが考慮されます。
利用権設定の廃止について
利用権設定による農地の貸し借りは、2025年3月31日で廃止され、2025年4月以降は、農地中間管理機構(農地バンク)を利用した貸借、または農地法第3条による賃借を行う必要があります。
3. 農地取得・賃借の手続き

農地バンク(農地中間管理機構)の活用
国が認定する「農地中間管理機構(いわゆる農地バンク)」を利用することで、農地の借り受け先を探しやすくなっています。都道府県ごとに設置されており、農地所有者が農地バンクに農地を預け、新規就農者や拡大を目指す農家がそこから借りる仕組みです。
- メリット:マッチング支援が充実しているため、新規就農者がスムーズに農地を確保しやすい。
- デメリット:人気のある地域では希望の条件に合う農地がすぐに見つからない場合も。
農地取得・賃借の流れの一例
- 地域や農地の情報収集:市町村やJA、移住相談センターなどに問い合わせる。
- 農業委員会に事前相談:取得・賃借の許可条件などを確認。
- 契約(売買・賃借)交渉:条件を詰めて契約書の作成。
- 許可申請:農業委員会に申請書類を提出。
- 許可取得→契約成立
ポイント:契約を正式に結ぶ前に、農業委員会の許可が必要となるため、事前の相談・申請手続きが欠かせません。
4. 地方移住で利用できる主な補助金・助成金
移住支援金
自治体によっては、「移住支援金」や「移住定住促進事業補助金」 などの名称で、引っ越し費用や住宅改修費の一部を助成している場合があります。
- 対象:首都圏からの移住者や、地域創生に寄与する事業を行う移住者など
- 支給額:数十万円~数百万円(自治体により異なる)
4-2. 空き家バンク
自治体が運営している「空き家バンク」を利用して、低価格で古民家などを借りる・購入する ことが可能です。改修が必要なケースも多いですが、リフォーム費用の助成制度を設けている自治体もあります。
5. 新規就農者向け補助金・支援制度の例
就農準備資金
農林水産省が実施している「就農準備資金」は、研修期間中の生活費等を支援 する制度です。
- 対象:就農研修を受ける新規就農希望者
- 支給額:12.5万円/月(150万円/年)
- 期間:最長で2年間
経営開始資金
新たに農業を開始する場合、経営開始資金 の支援が受けられることがあります。
- 対象:認定新規就農者など
- 支給額:12.5万円/月(150万円/年)
- 期間:最長で3年間
地域独自の新規就農支援
各自治体によっては、独自の就農支援制度(補助金・助成金)が設けられています。自治体の農政課や移住担当窓口 に問合せ、該当の制度がないかを確認しましょう。
6. 農業法人化やビジネス展開を視野に入れる場合

農業法人設立のメリット
- 法人化による信用度の向上
- 補助金・助成金の選択肢拡大
- 従業員の雇用や規模拡大がしやすい
農業法人設立の際には、会社法や農地法、農業経営基盤強化促進法などの関連法令の知識が必要になります。設立手続きや必要書類の作成 をスムーズに行うためにも、行政書士などの専門家への相談がおすすめです。
六次産業化への取り組み
農産物の生産だけでなく、加工・販売までを一貫して行う「六次産業化」によって、付加価値を高める ビジネスモデルがあります。
- 設備投資に対する補助金や融資制度 が利用できる場合もある
- 地域ブランドの確立や観光農園との連携 などを行うことも可能
7. 農業を始めるにあたって押さえておきたいポイント
- 地域とのコミュニケーション
- 農業は地域との連携が欠かせません。移住前の見学や交流会への参加などで、コミュニティづくりを行っておくと良いでしょう。
- 初期費用と収支計画の把握
- 農機具や資材の購入費、ビニールハウスや施設の建設費 など、初期投資が必要です。資金計画を立てたうえで、補助金・助成金や融資を活用しましょう。
- 研修制度の活用
- 農業経験が少ない場合は、JAや自治体、農業大学校などが提供する研修制度を活用し、実践的な技術や経営ノウハウを学ぶと良いです。
- 専門家への相談
- 農地法に関する手続きは複雑な場合が多いため、行政書士などの専門家に相談しながら進めましょう。
8. まとめ:行政書士を活用してスムーズな農業スタートを

地方移住で農業を始めるには、農地法の理解 や 農地取得(または賃借)の許可手続き、自治体ごとの 補助金・助成金制度の調査 などが必要不可欠です。特に、新規就農者向けの支援制度は多岐にわたるため、自分が利用できるものをしっかりと把握し、計画的に活用することでリスクや負担を軽減できます。
行政書士事務所では、農業関連の各種許認可申請や法人設立支援、補助金申請サポートなど、手続き面のサポートを行っています。複雑な法的手続きに不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。スムーズな農業スタートを実現するために、一緒にサポートさせていただきます。
【当事務所のサポート内容】
- 農地取得・賃借に関する農業委員会への許可申請手続き
- 就農準備資金・経営開始資金などの補助金申請手続きサポート
- 農業法人(株式会社・合同会社・農事組合法人など)の設立サポート
- 移住支援金や空き家バンクの利用に関する情報提供・相談窓口のご案内
農業を通じて地方の暮らしを充実させたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。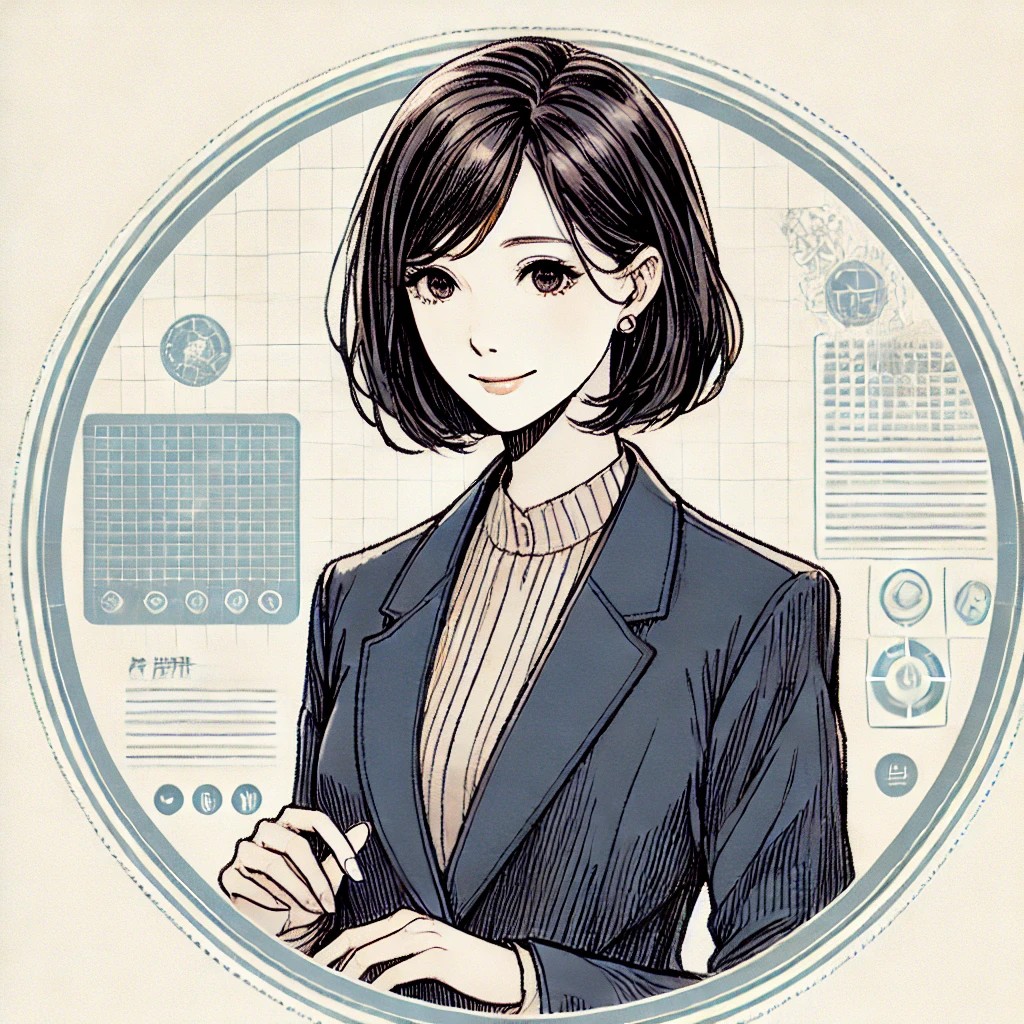
お気軽にご相談ください
農地転用許可の申請プロセスは煩雑で、適切な知識、多くの書類の準備が必要です。特に図面の作成等には大変な手間がかかります。行政書士かわいあい事務所ではこれらの書類の作成、申請手続きのアドバイス、事前相談から許可取得までのプロセス全般をサポートし、スムーズな手続きを実現します。
また、地方移住をお考えの方には不動産をお探しするお手伝いもできますので、お気軽にご相談ください。